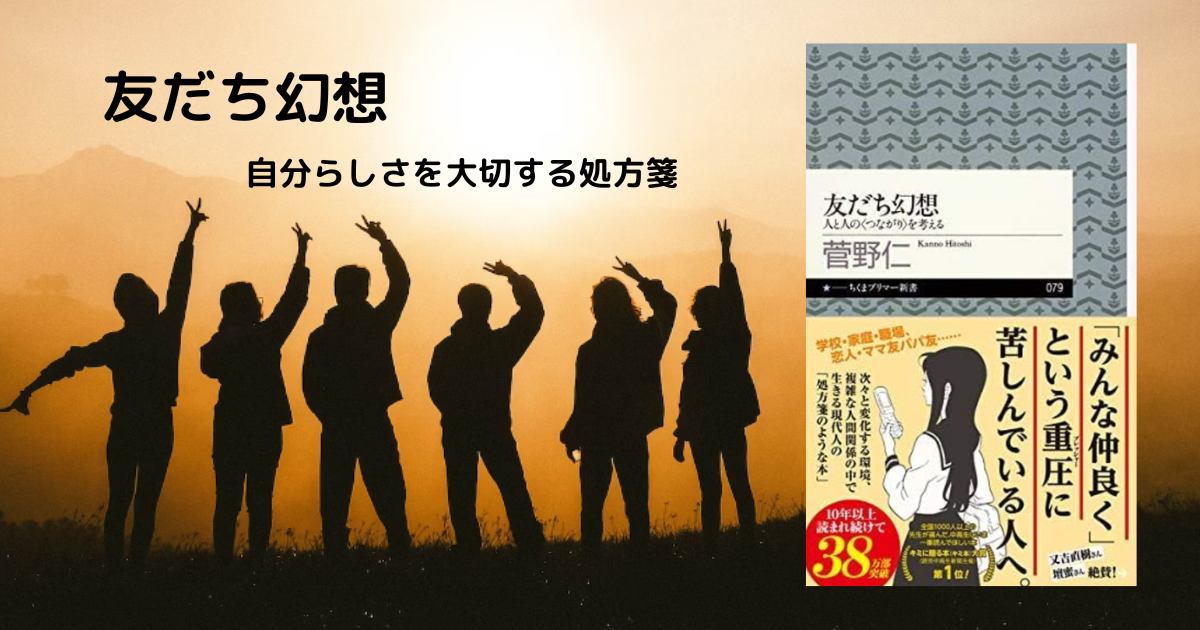
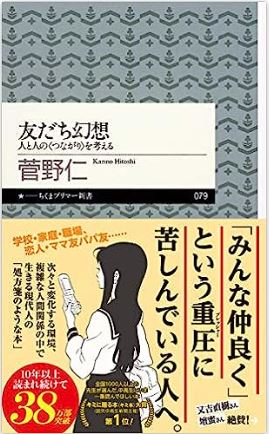
人付き合いを義務と感じないために
みんなと仲良くしなければいけない。
友達の期待にはこたえなければ今後の関係に影響が生じる。
自分にとってはそれほど価値観を感じない関係性にどれだけ意識を傾ける必要があるのでしょうか?
もっと自分らしくいるために、〇〇でなければいけないという自分を押し殺してしまうことはしなくてもいいのです。
【スポンサーリンク】
■友達幻想の概要
あの又吉直樹さんがテレビで紹介していたことでも有名な「友達幻想」。
人付き合いが大変なこの時代に効く処方箋のような本という装丁帯のメッセージも印象的です。
人との付き合いに窮屈さを感じる人は必ずいるはずです。
なにを隠そう私自身がそうなのです。
・もともと人付き合いが苦手な自分
・話すことが苦手な自分
・しかし、付き合いも大事だと思ってしまう自分
こんな私にとって目を引かないはずがないメッセージでした。
この本はそんな窮屈に考える必要がないことを教えてくれる内容になっています。
人付き合いのルールを知り、少しの作法を身に付けるだけで、複雑な人間関係の中で自分が必要以上に傷つかず、しなやかに生きられるよう指南してくれます。
■この本から感じる自分

仕事の性質上でいろいろな人と接し、会話もしている自分がいます。
そんな自分は周囲からみればうまくコミュニケーションが取れる人と見えているかもしれません。
でも実際はそんなことはありません。(本人が一番よくわかっています)
できれば早く一人になりたい。
多くの人といる場面から離れて、できるだけ早く家に帰りたいという気持ちがいつも生じます。
その分、自分を見ていてほしいとか、認めてほしいなどの承認欲求は人よりも低いと思います。
人付き合いに対してもっと気楽な気持ちになれればいい、人との適切な距離感は自分が決めていけばいいのだという・・・
自分にとっては読んでほっとするような内容でした。
■悩む必要はなかったんだ

ここ数年のコロナの状態で一層人との交流に抵抗を感じるようになってしまった人もいるのではないかと想像します。
でも無理をして自分の気持ちを抑制してまで人と同調する必要があるのかというとそんなことはないと個人的には思います。
人と交流する機会は、自分が成長するひとつの特別な場面としてとらえてある意味チャレンジの機会(特別な機会)と感じてみてもいいかもしれません。
もともとできる人に合わせる必要はないし、いろいろな人と同調できる人が評価されるのかと言うと本来はそうではないはずです。
個人個人にはそれぞれの持ち味(価値観)があります。
その価値観は人に押し付けるでもなく、押し付けられるでもないのです。
この本を読むことで少し気持ちを楽にすることができると思います!
|
|
【スポンサーリンク】
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=12831779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7807%2F9784480687807.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
