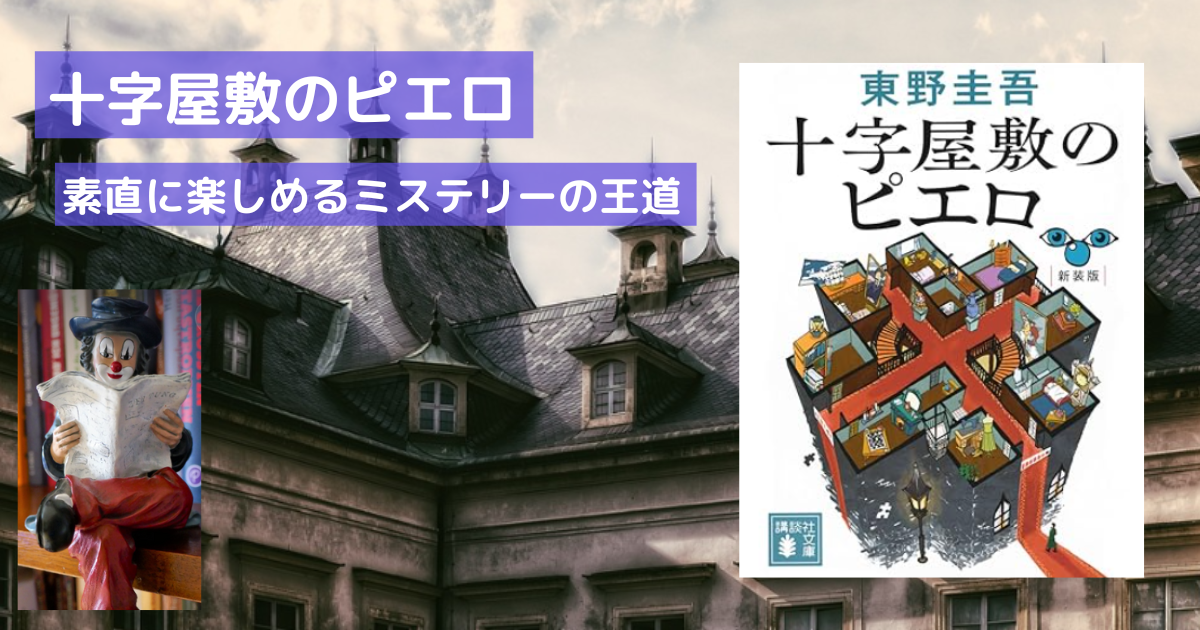
十字屋敷の主人である「頼子」がバルコニーから転落死した。親族が法要に集った夜、次の主と秘書が刺殺される。外部犯なのか、あるいは親族の犯行なのか?
東野先生の初期の作品(1992年なので今から33年も前なのですね)ですが、私は今まで読んだことがありませんでした。
昔の作品と言えども書店を物色するといつも注目コーナーには陳列されているということもあり、いずれは必ず読んでみようと思って入手していたものです。
そしてこの度、落ち着いて楽しむことができましたので、この作品を私の視点で紹介をさせてもらおうかと思います。
もともとミステリー好きの自分にとっては、この十字形の特殊な屋敷であること。
そしてそこで生じる事件を解決していくというようなお話には真っ先に食いつくべきだったのですが、なぜか読まないままになってしまっていました・・・
読了後の満足感は非常に高く、もっと早く読んでおけばよかったなあと後悔しています・・
【スポンサーリンク】
■十字屋敷という特殊な形の屋敷

綾辻行人先生の「十角館」などもそうですが、現実的にはなかなかありえないような様相をした建物が登場し、そしてその閉じられた状況の中で巻き起こる事件、いわゆるクローズドサークルというものは、ミステリー好きにとっては大好物の設定です。
よくこの手のお話の冒頭には屋敷の見取り図などがガイドとして掲載されています。
お話によっては構造が複雑なケースも多々あり、私は時々そのページをコピーして手元に置いておくこともします。
この十字屋敷も同じように見取り図が掲載されているのですが、(冒頭ではなく、かなり終盤ですが)他の作品に比べるとその構造は非常に分かりやすく、読み進めていくのに悩むことがありません。
それだけお話に集中できるので、ミステリーを読み始める方にとっては適切な1冊なのではないかと感じます。
■理解しやすい登場人物関係

そして建物の分かりやすさに加えて、登場人物とその関係性についても、非常に分かりやすいのです。
たくさんの登場人物とその関係性が複雑であると、苦手な方は読むことが苦痛になってしまうこともあるかと思います。
私もあまりに複雑な場合には、相関関係図を自分で書きながら読み進める時もあります。でも、このお話では結構すんなりと登場人物が自分の中に定着しますので心配いりません。
適切な人数と関係性が、やはりこれもお話の内容に集中できるようになっていますので、読みやすい要素となっているのだと感じますね。
■ストーリーをとらえやすくするピエロの登場

そしてこのお話でストーリーをとらえやすくしてくれている最大の工夫は、ピエロという人形を登場させているところです。
時々ですが、屋敷に置かれたピエロの目線から状況や登場人物の様子を語る場面が出てきます。
もちろんピエロは動き回ることはしませんが、あえてその置かれた位置からピエロが見えたこと、感じたことを登場人物の目線とは全く異なる方向性で読者に教えてくれているのです。
それが事件の解決のヒントになったり、お話そのものを読者にとって理解させやすくしてくれたりしています。
今まであまりこのような設定を見たことがなかったので、非常に新鮮に感じました。
■しっかりとぞっとさせてくれる要素
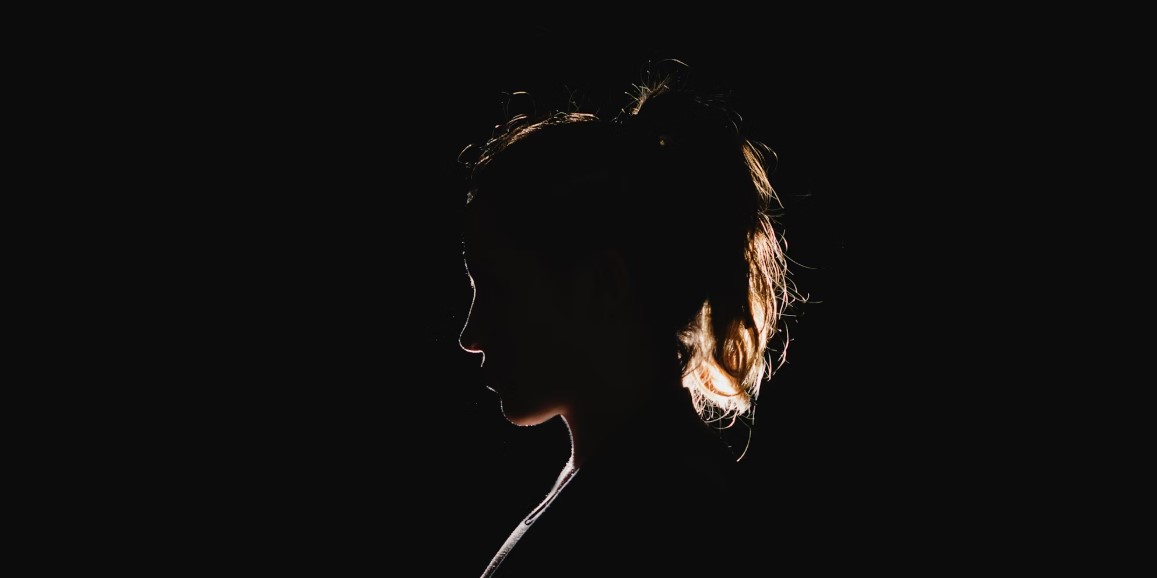
登場人物のひとり「水穂」という女性とピエロの持ち主である人形師の「悟浄」が対話の中で徐々に事件の真相を解明していく流れなのですが、その展開が非常に素直できれいに感じます。
読み進めてきた、それぞれの登場人物の言動や関係性の整理をすることによって、次々に新しい事実が分かり、そしてこの屋敷ならではのトリックもあわせ、それをつなぎ合わせて、真相を突き止める様は読んでいて楽しさを感じるものです。
しかし、最後は少しぞっとするような内容が含まれています。
静かな中にも恐ろしい考えが隠されている・・・
読んでいる自分としても「やられた!」というよりも、少し気持ちが重たくなるような瞬間でした。
最後の最後まで、読者感情をコントロールしてしまうことを忘れない、優れた作品だと実感しました。
【スポンサーリンク】
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=21437987&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8786%2F9784065378786_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
