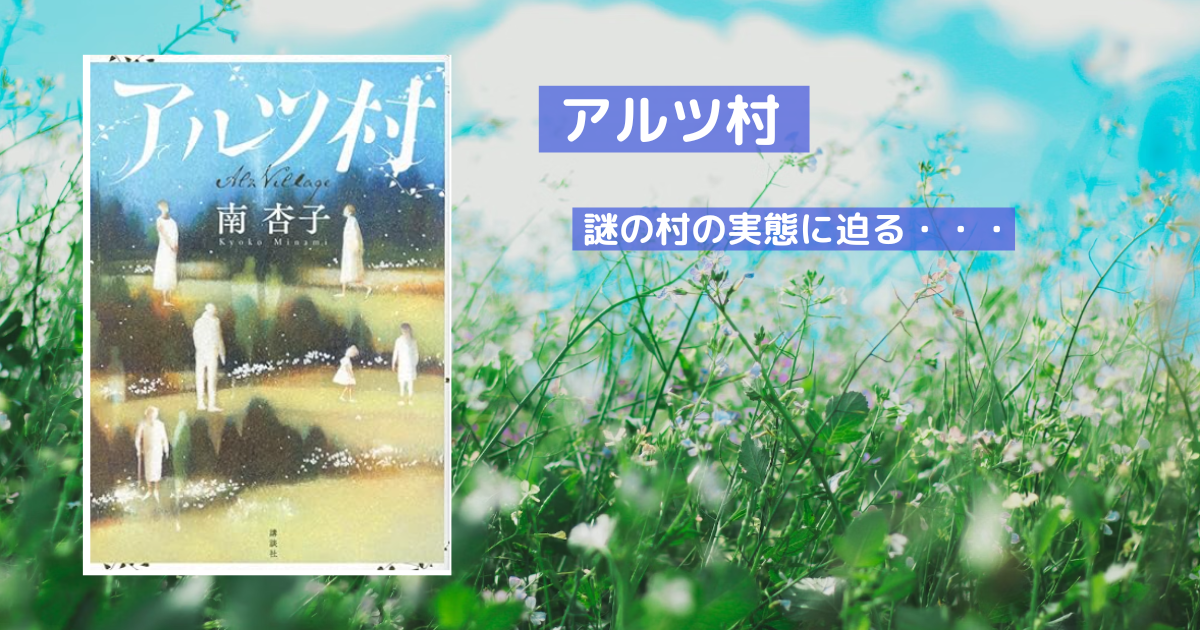
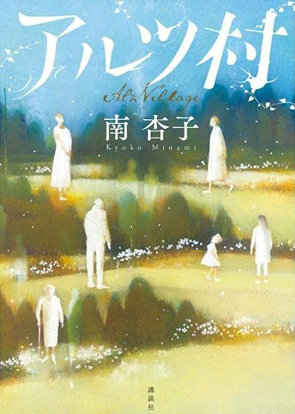
高齢者だけが身を寄せ合って暮らす山間の村。
そこは楽園か、遺棄の地か。
世界一の認知症大国、日本。
人生を否定される患者生活を破棄される家族・・・・・
【スポンサーリンク】
■アルツ村あらすじ
日々夫のDVにダメージを受けていた三宅明日香は、その生活に耐え切れず、娘を連れて家庭からの逃亡を図ります。
車で逃亡していた明日香は、逃げている途中に予期せぬトラブルに巻き込まれ、事故に合います。
そして意識を取り戻した時、明日香にとってとても過ごしやすいある謎の村に保護されていました。
そこは認知症を患った老人たちが穏やかに暮らす誰にも知られることのない、ある村でした・・・
そして時の経過とともにさまざまな事実がわかっていくのです。
■認知症は身近なテーマ
 認知症は若年者も含めて、最近では現代病の一つとしてポピュラーになっているかと思います。
認知症は若年者も含めて、最近では現代病の一つとしてポピュラーになっているかと思います。
若いうちから、生活習慣が乱れることは認知症を誘発する危険が高まると注意を促した情報もあるほどです。
今だに完全な治療法は見つかっておらず、いざその状態になった場合にはその身内の方のサポートの負担は計り知れないものがあると思います。
このお話はそのサポート側の重たい心理を汲み取った内容と言えるかもしれません。
■アルツ村を読んで感じること
お話にもあるのですが、認知症となった高齢者の方々は日々を自分なりのペースで穏やかに生活しています。
本当に素直な気持ちで生きていることが伝わってきます。
サポート側の人たちの負担を考えたしくみも理解できるものの、姥捨て山的な印象も受けるため、正直複雑な心境でした・・・・
現代の大きな問題点としてもこの物語は深く受け止めることができました。
そして、最後には驚愕の事実も・・・・
身内に認知症の方がいらっしゃるという方はまた違った受け止め方をされるかもしれません。
すこし気持ちが重たくなるお話かもしれませんが、自分自身にとっては読んで良かったと思える本です。
【スポンサーリンク】
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=20606637&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6588%2F9784065266588.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
