
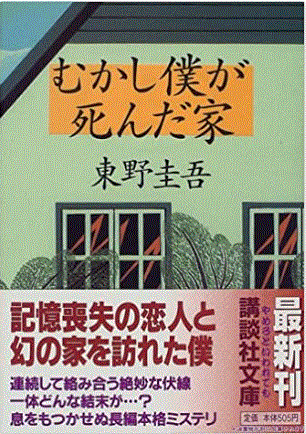
「あたしは幼い頃の思い出が全然ないの」。
7年前に別れた恋人・沙也加の記憶を取り戻すため、私は彼女と「幻の家」を訪れた。
それは、めったに人が来ることのない山の中にひっそりと立つ異国調の白い小さな家だった。
そこで二人を待ちうける恐るべき真実とは……。
【スポンサーリンク】
■ストーリー展開の印象

かなり以前から積読本として所有していたのですが、ビジネス書を見る機会が多い中で、ちょっと息抜き的に読んでみることにしました。
東野圭吾さんのお話はその他にいつも楽しく読ませていただいています。
作品ごとにいろんな雰囲気を醸し出してくれる多彩さも魅力のひとつと感じています。
今回読んだ「むかし僕が死んだ家」は登場人物も少数に限定されていることと、リアルメインストーリーに出てくるのは2人だけ。
名前が明かされていない「私」とかつての恋人「沙也加」の2人だけです。
その2人のやりとりはまるで、演劇を見ているような感じで進んでいきます。
■沙也加の記憶
沙也加の記憶を取り戻すため、沙也加の父が残した手がかり(家の鍵)をたよりにして実際にその家に出向きます。
出向いたその家に残されたものを少しずつたどることにより、徐々に沙也加の過去の記憶と事実が分かり始めるのです。
徐々に分かる事実がさらにその先を知りたいという欲求につながるため、読者側としてはやめられなくなる状態になってしまいます。
結果、引き込まれてしまうわけです。
この話の展開にこそ読者をひきつける巧みさがあると感じます。
【スポンサーリンク】
■たどりつく結末

結果として、最後にたどりついた事実が沙也加にとってどういう影響を与えたのか?は読者それぞれの方の受け取り方になるかと思います。
そして、これは情報として得た事実ですが、物語に出てくる「私」は物理学部助教授・・・とのこと。
後に東野さんが出される作品につながる要素も持ち合わせているということに驚きました。
作品を超えた、別の視点での楽しみもあるというところが、東野作品の魅力でもあるかもしれませんね。
【スポンサーリンク】
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3733fdc0.50f9939d.3733fdc1.5ab78d2c/?me_id=1213310&item_id=10632746&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5073%2F9784062635073.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
